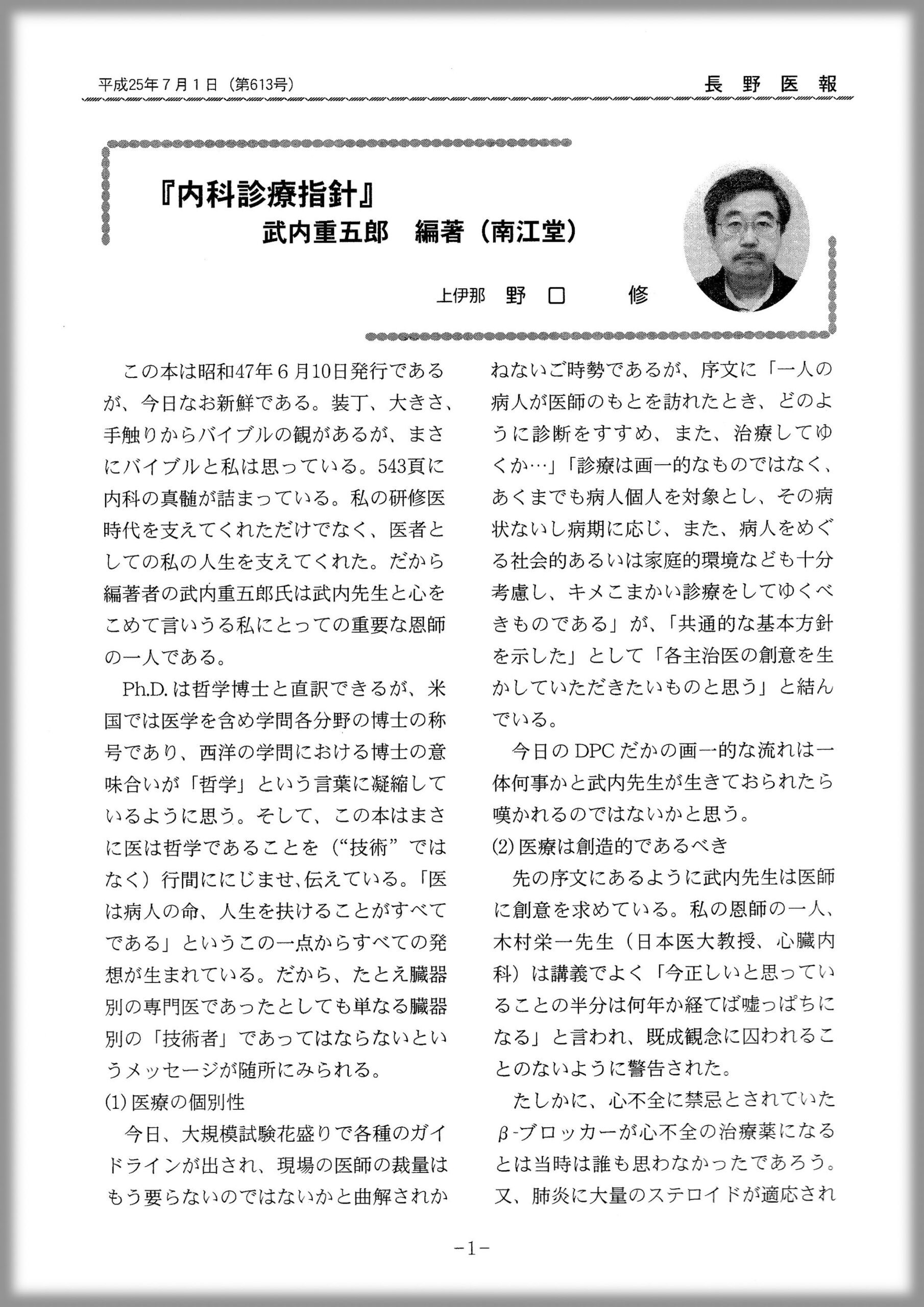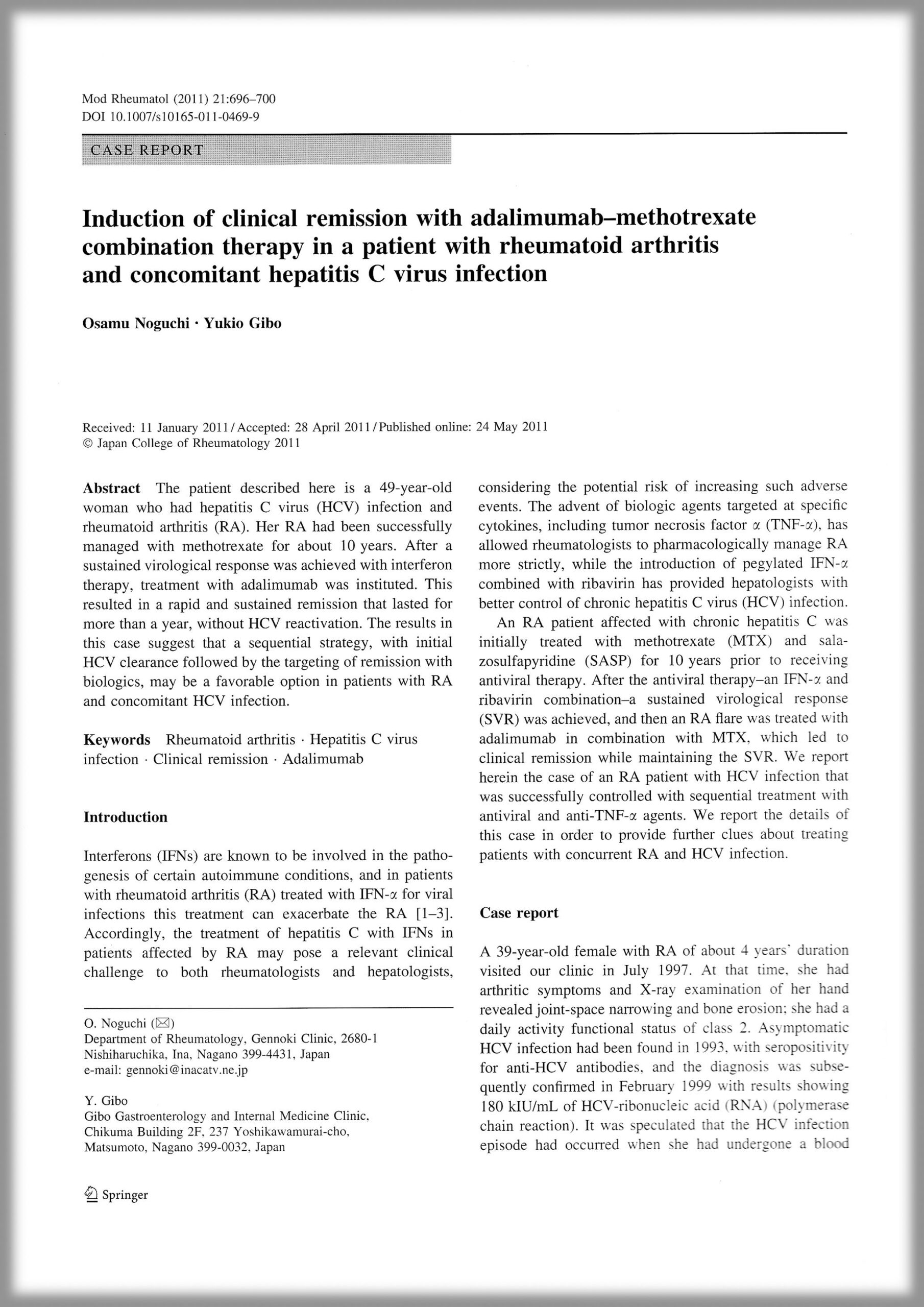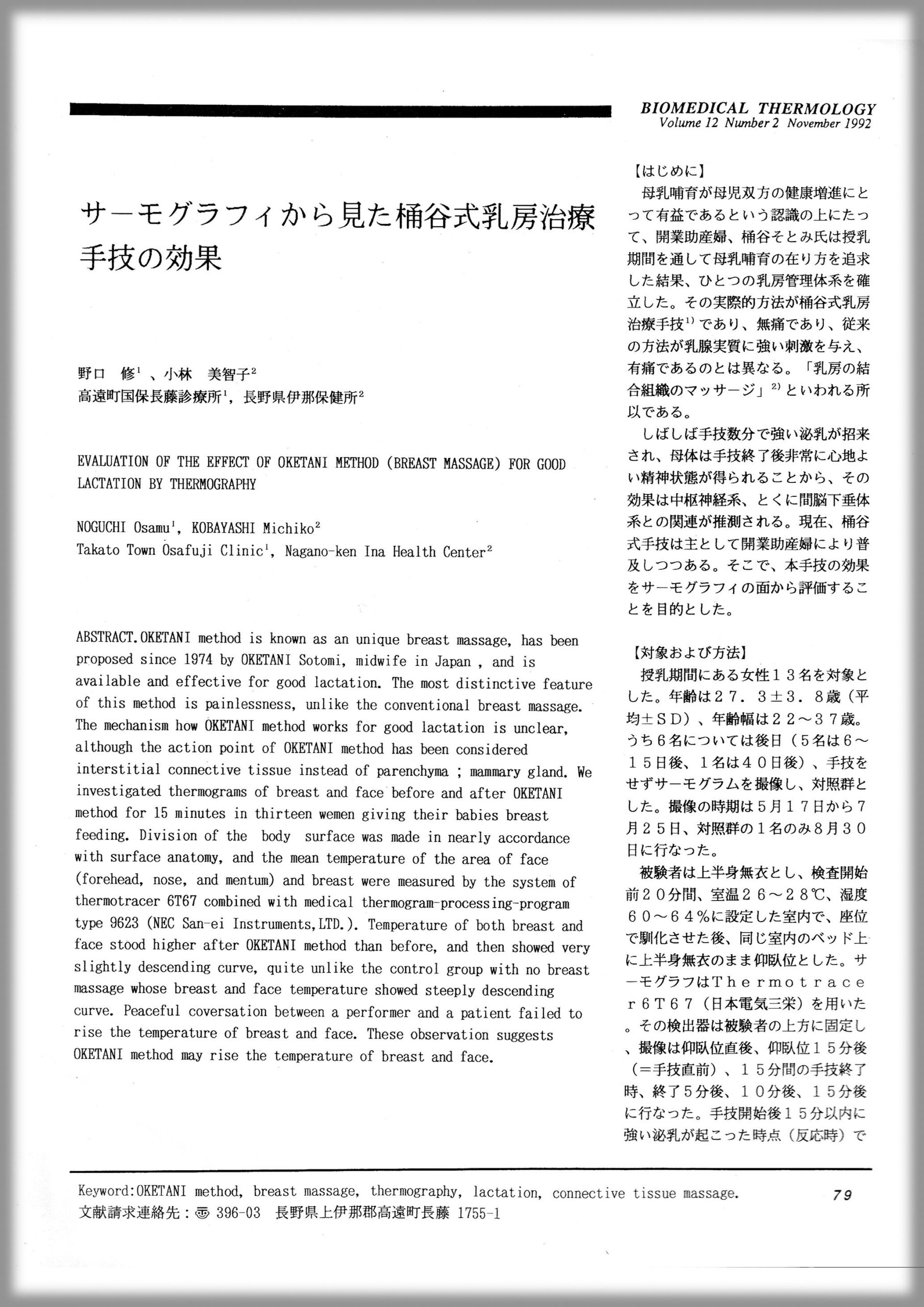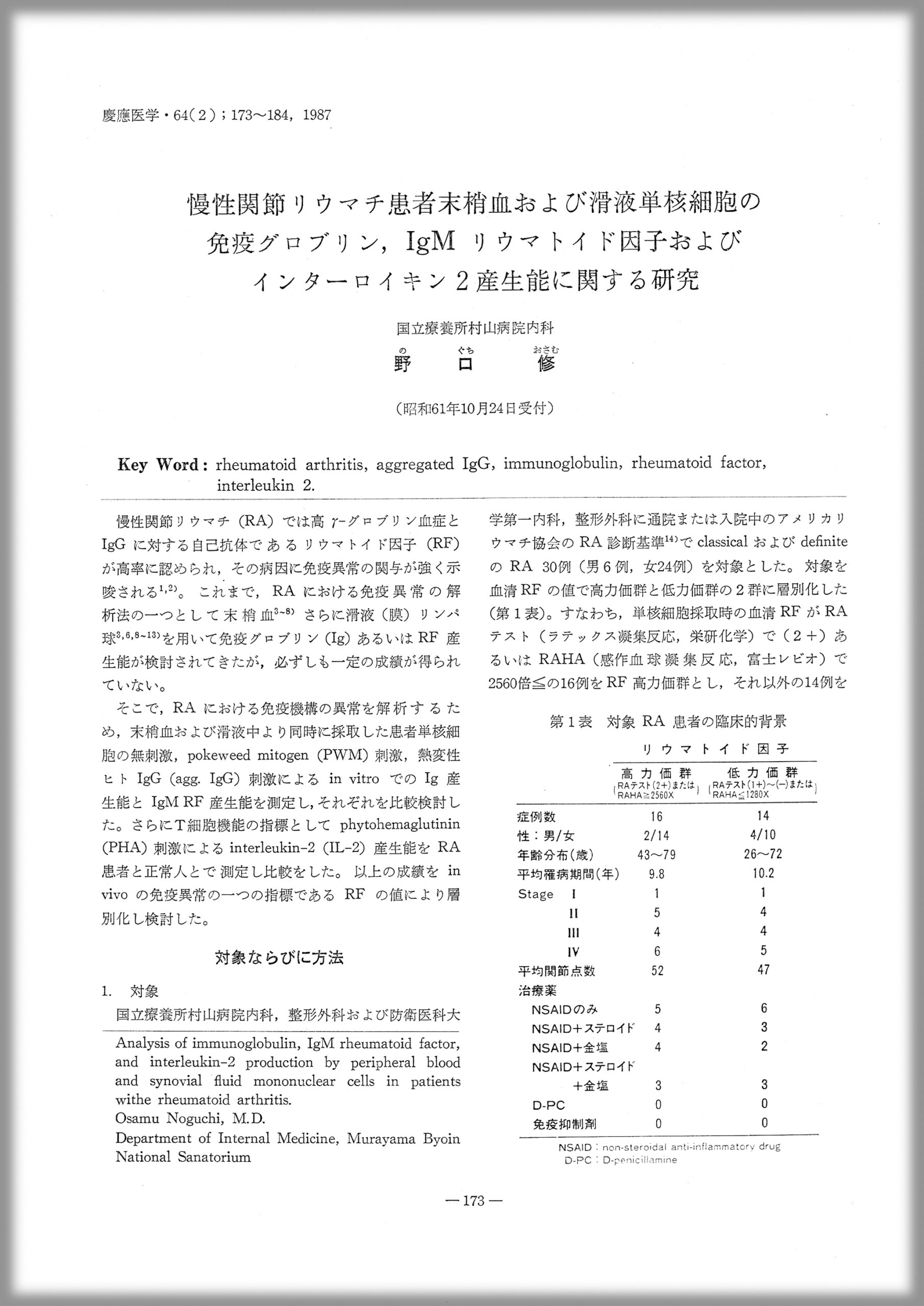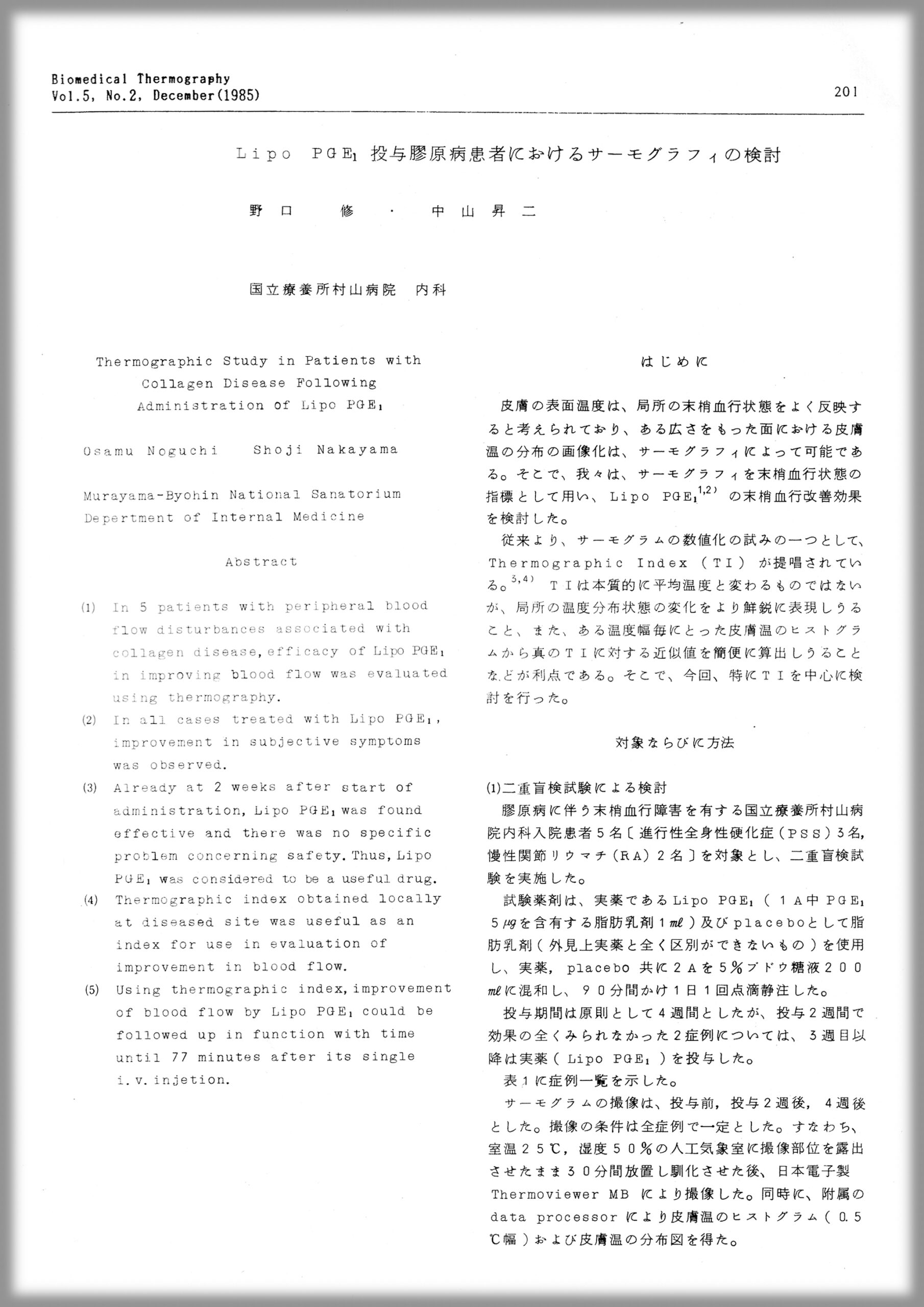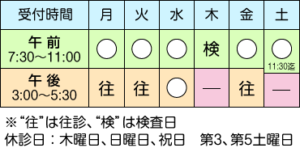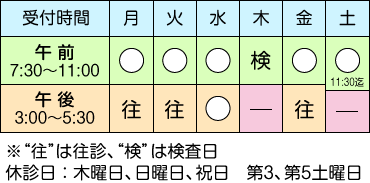- Home
- 院長論文
院長論文
院長が過去に提出した6本論文です。
画像をクリックすると【PDF】ファイルが開きます。
フリーアクセスの出版社ウェブサイト(欧文サイト)に院長の投稿が採用されました。閲覧、ダウンロード、印刷のいずれも無料です。
B型肝炎ウイルス(HBV)既感染の関節リウマチ患者においてはMTX惹起性血清ALT上昇が抑制されている
関節リウマチ(RA)の標準的治療薬であるメトトレキサート(MTX)内服治療でしばしば薬物性肝炎(ALT上昇=MTX肝炎)が起こることが知られている。一方、HBV既感染者のHBVは肝細胞核内に潜在し言わば休眠状態で通常は肝炎を起こすことはないが、RAではその治療薬の関係で(リツキシマブ等の生物製剤や抗癌剤、更には稀にMTXでも)HBVが再活性化され突然重篤な劇症肝炎を発症することがありそれは殆ど致死的であるため日本リウマチ学会や日本肝臓病学会において臨床医に向けて注意喚起がなされている。
しかしながら医療の現場では一般的に短絡的にRAにおける肝障害は背景に肝炎リスクのあるHBV既感染者で起こりやすいのではないか、そして起きた場合には危険ではないかということが言われて来た。しかし実際は狭義のHBVキャリア(HBs抗原陽性者)に長年MTXを投与してきても何も問題がないという現実を臨床現場でリウマチ専門医は知っていたのでde novo肝炎を恐れて定期的に高額なHBVーDNA検査をしたり抗ウイルス薬を予防投与することに若干の違和感を正直覚えたのは事実であった。
そこでMTX肝炎とHBVとの関連を検証しようというのがこの臨床研究への取り組みの動機であり、私自身もおぼろげにHBV既感染者ではMTX肝炎は起こりやすいであろうという根拠のない結論を予想していたのであるが、結果は全く逆でHBV既感染者ではMTX肝炎は有意に起こり難いという事実が導き出されたのである。それでは何故生物製剤(バイオ)投与患者(殆ど常にMTXも併用されている)ではde novo肝炎が起きやすいのか。このメカニズムについても大胆なしかし論理的整合性のある推論を提示させていただいた。
在宅認知症患者の訪問診療の中で見えた介護保険サービス利用の不均衡について
はじめに
2000年4月より実施された、介護の社会化ということを理念の一つとして掲げた介護保険制度は、主たる介護者となることが多かった嫁や配偶者等の介護負担を軽減するうえで大きな意味があった。
介護保険サービスには居宅系と施設系、そして地域密着型介護系の大きく三つがあるが、今回2005~2006年度中にかかわった在宅認知症患者に関して世帯別に検討すると、その介護サービスの使い方に特徴が見られた。
小数例での検討ではあるが、17年間、農村地域での在宅医療の日常で経験してきた印象と一致するものであり、今後のケアマネジメントの一参考資料として有用と考え報告する。
リウマチ科診療所におけるインフリキシマブの使用経験を通じてリウマチ科診療所のあり方を考える
はじめに
今日、病院勤務医の疲弊の原因の一つは患者が過度に集中することが指摘されている。
病院勤務医の負担を軽減するためにはそれゆえ、診療所は軽症例だけでなく、ある程度病状の重い症例をも担うことが求められるということを、暗に示唆する表現がいろいろの文献・文書に散見される。
診療としての役割分担の中身が今日より厳しく問われているといえる。
診療所は従来の外来医療を見直すとともに、在宅医療担当能力を含め、その潜在能力をより高め、従来は担いきれないとした病状を示す症例をも治療・管理することが今日必要となった。
病院勤務医の疲弊に対して我々開業医の支援にもおのずと限界があるが、病院信仰を生み出す土壌をわれわれが変わることで改善してゆく努力も必要であろう。
当院では関節リウマチ(以下RA)のインフリキシマブ(以下IF)による治療に取り組む中で必然的にリスクの高い医療を担うこととなった。
そこでその取り組みの経験をまとまたので報告する。この取り組みはより近くのリウマチ専門医でリウマチ専門医療を受けたいという患者のニーズにも合致するものである。
リウマチ治療のトレンドが新しい時代へと突入した中で、わが国の医療制度の近未来の変革とからめてリウマチ科診療所のあり方を考えてみたい。